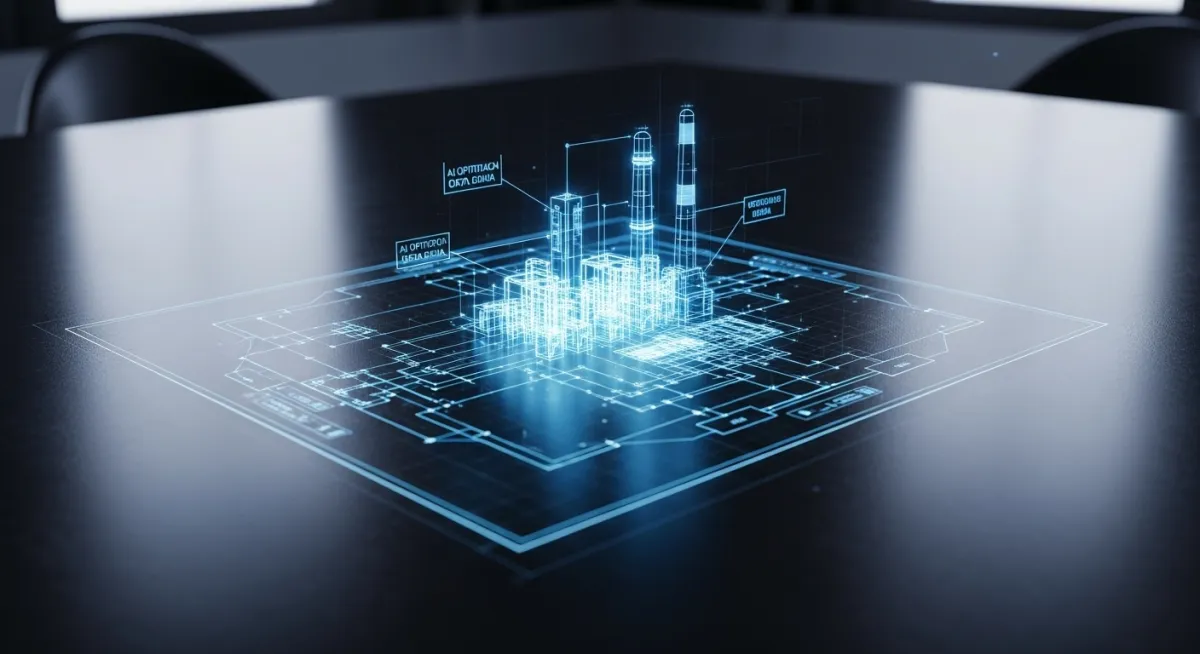
SNSから製鉄業へ:「製造業AI」は、いかにして次なる産業革命を鍛え上げるのか
テック起業家が挑む、製鉄業の再構築
ソーシャルメディア分野で知られる起業家が、製鉄という伝統産業の変革に挑んでいます。人気写真アプリ「Dispo」の共同創業者であるダニエル・リス氏が率いるスタートアップ、Nemo Industriesは、AI活用を軸に製造業の基幹セクターである製鉄の再興を目指しています。
同社の中核ミッションは、インテリジェントオートメーション(AIによる自動化)を活用し、垂直統合型の製鉄企業をゼロから構築することです。AIを起点とした“ネイティブ”なプロセス設計により、リス氏は既存の競合に対して20〜30%という高い利益率を実現できると見込んでおり、生産性と効率性の新たな基準を打ち立てようとしています。
背景にあった「国家安全保障」への問題意識
この大胆な事業転換は、企業内の経営会議から生まれたわけではありません。発端となったのは、2023年に米国防大学で行われた国家安全保障をテーマにしたウォーゲーム(軍事シミュレーション)でした。
シナリオは南シナ海での有事を想定しており、その中で明らかになったのが、米国の産業基盤における構造的な脆弱性でした。特に、造船や防衛に不可欠な鉄鋼の国内生産能力が著しく不足していることが問題視されました。これを受けてリス氏は、鉄鋼サプライチェーンの再構築を新たなミッションとして掲げるに至ったのです。
Nemoが描くAI駆動の製鉄インフラ構想
Nemo Industriesは、鉄鋼業界が長年抱えてきた非効率性を根本から解決するために設立されました。同社は、AI技術を駆使して、鉄鋼の中間製品である銑鉄(せんてつ)の生産工程を最適化しようとしています。
従来の業界では、依然としてスプレッドシートや人手による管理に依存する場面が多く、これが生産の拡張性を妨げていました。Nemoはこうした旧態依然とした手法からの脱却を図り、AI主導の効率的なプロセスを導入します。
さらに同社の取り組みは、単なるソフトウェア提供にとどまりません。AIの利点を最大限に引き出すため、自社で最新鋭の溶鉱炉を建設・運用する方針を打ち出しています。
サステナビリティと収益性の両立を目指して
Nemoの事業計画には、環境配慮の視点も組み込まれています。燃料には石炭ではなく、よりクリーンな天然ガスを使用し、加えてCO₂の回収技術の導入も積極的に検討中です。
こうした環境対策は、インフレ抑制法(IRA)による税制優遇の対象となる可能性があり、持続可能性だけでなく、経済的にも高い収益性を見込める構造となっています。
豊富な資金と実績ある経営陣による盤石な体制
このようにスケールの大きな構想を実現するには、潤沢な資金と専門的な知見が不可欠です。リス氏は、エネルギー大手シェニエール・エナジーで数十億ドル規模のプロジェクトを主導してきたマイケル・デュボス氏を経営陣に迎え、体制を強化しました。
この布陣の下、Nemoはすでに初期資本として2,820万ドル(約42.3億円)を確保。現在はさらなる成長に向けて、既存投資家らとともに1億ドル(約150億円)規模のシリーズAラウンドの資金調達を進めています。
また、米南部の2州からは、今後15年間で3工場を建設することを条件に、総額10億ドル(約1,500億円)を超える優遇措置の提案も受けており、同社への期待の高さがうかがえます。
製造業の未来にベンチャー級のリターンを
リス氏は、「最も大きな投資機会は、多くの場合、基幹産業の再生にこそある」と述べています。鉄鋼業のような成熟セクターに最新技術を取り入れ変革を図ることは、かつてのカーネギーやロックフェラーのように、巨額のリターンを生み出す可能性があると考えています。
Nemo Industriesは、製造業向けAIを応用することで、「次の偉大なイノベーションは、最も古典的な産業から生まれる」ことを証明しようとしているのです。
まとめ:製造業×AIが切り拓く次世代の競争軸
Nemo Industriesの取り組みは、一企業のスタートアップにとどまらず、今後の産業戦略全体を見直すうえで重要な示唆を含んでいます。AIによる本質的な変革の場が、ソフトウェアから製造・重工業といったリアルな現場へとシフトし始めていることが明確に示されています。
ここで示唆される最大のポイントは、既存のプロセスにAIを単に“追加”するだけでは、競争優位は築けないということです。Nemoが実践するように、事業の企画段階からAIを基盤に据え、設備やオペレーションのすべてを再設計する「AIネイティブ」なアプローチこそが、生産性と利益率の飛躍的な向上につながる鍵となります。
また、地政学的な緊張やサプライチェーンの脆弱性といったマクロ環境の変化が、新たな巨大市場を創出するトリガーになっている点も見逃せません。国家安全保障という視点から始まったこの挑戦が、結果的に産業変革と巨額投資を呼び込んでいるのです。
テクノロジー業界の旗手が製鉄業に参入するというこの流れは、次世代の偉大な企業がソフトウェア分野に限らず、基幹産業の再構築からも生まれることを示しています。これは日本のビジネスリーダーにとっても、自社の資産や技術を見直し、新たな成長の道を見出すための大きなヒントになるはずです。
最新ニュースは以下をご覧ください: https://aipulse.jp/blogs-3259-8285

